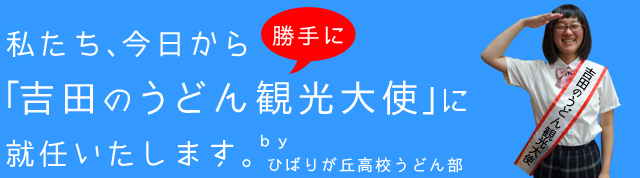
「吉田のうどん」の特徴

特徴
「吉田のうどん」とは、主に山梨県富士吉田市を含む郡内(ぐんない)地方で食べられている郷土料理です。強くてコシの強い麺、馬肉、キャベツを使用したトッピング、味噌と醤油をあわせたつゆが特徴です。また、「すりだね」と呼ばれる辛味を入れて食べるのも、「吉田のうどん」ならではと言えます。ただし、これはあくまでも一般的な話であって、明確な基準があるわけではありません。店によっては、牛肉や豚肉を使用している店もあります。それは、「吉田のうどん」がそれぞれの家庭で食べられてきたものを外食として提供するようになったからであり、店ごとに様々な発展を遂げています。この自由さ、この懐の大きさが「吉田のうどん」なのかもしれません。
「吉田のうどん」の歴史

歴史
私たちの住む富士吉田市は、海抜高度652~850mの海から離れたとても寒い地域です。冬場の最低気温だけを見ると東北地方に負けない寒さが昔からあります。しかも、土地は富士溶岩の影響で、日本人の主食である稲作には向かない土地でした。そのため、大麦・小麦の生産が中心とならざるを得ず、稲作が農業の中心となったのは昭和に入ってからであり、富士吉田でうどんが作られるようになった背景には、このような事情がありました。元来、富士吉田におけるうどんは、正月や結婚式など晴れの日に供される特別な食べ物であり、日常食ではありませんでした。それが、交通網の発達により増加した登山客や、富士吉田の主要産業である織物を買い付けに来る人々に対して食事を提供するため、次第にうどん屋が軒を並べるようになったのです。さら に、大阪周辺から来る問屋が、土産としてうどんの玉を買って帰るようになるに至り、富士吉田のうどんは、主として地域外から訪れる人々に提供される食べ物として、地域に根付いていったのです。 富士吉田のうどんの特徴として、「麺の太さ・硬さ」が挙げられます。その由来としては、主要産業である織物業が女性中心であったため、力の強い男性がうどんを打ち、食事として用意したからだと言われています。
「吉田のうどん」と御師の家

吉田のうどんと御師の家の関係
「御師の家」と「吉田のうどん」は、一見なんの関係もないような気がしますよね。それがとっても関係あるんです。なぜなら、富士御師や、その他の参拝者など、富士山に参拝に行く人たちは、登山前に吉田のうどんの「湯もり」を食べていたそうなんです。ではなぜ吉田のうどんを食べていたのでしょうか?と、その前に「湯もり」とは、うどんの麺と、その麺を茹でたゆで汁をスープにして食べる、うどんの味そのものがわかるうどんです。うどんのゆで汁をそのまま使っているのでスープが白っぽくなるんです。そうです。白い麺に、白っぽいスープ。登山前に食べることで身を清めると考えられていました。
「吉田のうどん」と郡内織物

吉田のうどんと郡内織物の関係
富士吉田の主要産業である織物業は、主に女性が中心でした。そのため、食事を準備するのは男性の仕事でした。力の強い男性がうどんの麺を打ったため、「吉田のうどん」の特徴である、「麺の太さ・硬さ」が生まれたといわれています。その後、交通網の発達により増加した登山客や、織物を買い付けに来る人々に対して食事を提供するため、うどん屋が少しずつ増えていきました。現在では、富士吉田市内において60店以上のお店が存在し、地域のブランドとして確立され全国的に知られるようになりました。一見何の関わりもないような存在である「郡内織物」と「吉田のうどん」は、実は古くから深いかかわりがあったのです。
「吉田のうどん」とほうとう

「吉田のうどん」とほうとうとは?
「吉田のうどん」と「ほうとう」は山梨県の郷土料理です。見た目が似ているため同じように扱われがちですが、作り方や、食の地域は全く異なります。「吉田のうどん」は、麺を作るときに塩を使い寝かせてから茹でます。そして、具はシンプルにまとめます。一方「ほうとう」は、製麺するときには塩を一切使いません。そして、カボチャ、山菜、キノコなどの具をたっぷり入れてそのまま煮込みます。また、吉田のうどんは主に富士吉田地域で食べられてきましたが、「ほうとう」は、主に甲府地域をを中心に食べられるなど、さまざまな相違点が存在します。
「吉田のうどん」とほうとうの歴史
山梨県は、山間部が多いため米作りが厳しい土地柄でした。そのため、「吉田のうどん」や「ほうとう」の材料となる小麦が栽培されてきました。素材として小麦を使用することになった流れは同じですが、歴史に関しては「ほうとう」のほうが古いと考えられています。「ほうとう」の歴史については諸説ありますが、戦国時代に武田信玄が野戦食として戦場に持ち込み、自分の刀で食材を切ったことから「宝刀(ほうとう)」と呼ばれたという話があるほど、昔からなじみのあるものでした。一方、「吉田のうどん」については比較的歴史は浅く、明治初期に富士吉田の主要産業である織物を買い付けに来る人々に対して力の強い男性が食事としてうどんを提供するようになったのがはじまりだと考えられています。
「吉田のうどん」の不思議

「吉田のうどん」はおもしろい
富士吉田地域にとって「吉田のうどん」は、切っても切り離せないものですが、ほかの地域の人から見るととても不思議に思えることが多々あります。例えば昼食ですが、多くの人が迷わず「吉田のうどん」を選択し、毎日のように食べます。さらに、コンビニでも販売しているため、高校生のお弁当としてもよく用いられます。さらに、結婚式の締めには必ずといっていいほど「吉田のうどん」が出てきます。ほかの地域では考えられないことだと思いますが、「吉田のうどん」が出て来ない限り結婚式は終わらないのです。そして、1番の不思議が呼び方です。讃岐うどん、水沢うどん、稲庭うどんなど、さまざまなうどんが存在しますが、「の」をつけることはありません。しかし、山梨県の人は「の」をつけずに呼ぶことを大変嫌い、「吉田うどん」と呼ばれると必ずといっていいほど「吉田のうどん」だと訂正します。「の」をつける理由ははっきりわかりませんが、なぜか皆こだわります。